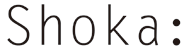写真 文 田原あゆみ
私はとうとうインドへ行った。
20代の頃に藤原新也氏の写真集を見ていつかインドへ必ず行こうと決意した。あくまで氏の視点で切り取ったインドの景色なのだということはわかっていても、ページをめくるたびに衝撃を受けた。聖なるガンジス川には人々の生活と死が混じり合って流れていて、そうだ生きるということは生々しいことなのだと、改めて目覚めたように感じた。パッケージング化が進み、生々しさが正気を欠いた時代に触れたからこそそのインパクトは大きかった。
インドに行きたい。けれどただふらふらと漂流するにはハードルの高い国だと感じた。何かこう崇高な、いや、現実的な目的がある時に行こう。そう決めた。ただふらふらといってしまったら、きっと私はまぶい(沖縄でいう魂。七つあるうちの4つを落とすとあの世へ行くと言われている。三つまでは落としても拾ったら大丈夫)を落としてしまうだろう。強靭な精神を持ち地に足が着いていないと、まぶいをかなり持っていかれる感が半端なく感じられたのだ。
2016年4月に家族ぐるみで親交のある東京のギャラリーfu do kiの浅野ファミリーから小林史恵さんを紹介していただいた。
(写真中央はその小林史恵さんと、インド・コルコタ発の手仕事布ブランドmaku textilesのデザイナーのSantanu氏。ベンガル料理の有名店にて仕事の打ち合わせをしているところなのです。クールビューティな目元がキリッとしていますね。)
小林史恵さんは奈良とインドを行き来してCALICO:the ART of INDIAN VILLAGE FABRICSの運営を指揮をとっている。CALICOの仕事は、インドの手織り手紡ぎの綿素材カディで作られた服の企画・デザイン・製作に関わる活動全般。彼女とそのチームの仕事は一言で紹介するのが難しいくらい多岐にわたり、今まで私が関わってきたアパレル業界の仕事のあり方とは様相が違っている。
まず驚いたのはとにかく同業者同士や、布の仕事に関わる人々との横の絆が強いということ。
インドの手仕事布が大好きで、とにかくそれに触れていたい、その布たちを多くの人たちに届けたい。彼女の中にあるその思いが軸となっていてぶれないのだろう。彼女にとって、同業者はライバルではなくてインドという国とその文化、そして手仕事布を愛する同志なのだ。
あまりに多岐にわたる活動をしているため、最初は漠然としていた彼女の活動。彼女に会うたびごとにその仕事の断片が一つずつ見えてきて、今では一枚の布のようにその全体像が見えてきた。きっと、そこに散りばめられた柄や微妙な色合いはこれから回を重ねるごとにまだまだ浮き上がってくるのだろう。
2017年に再会して、私たちはShoka:で2018年4月にCALICOの企画展をしましょうと、約束をした。そして慌ただしい年末に、そうだ、小林さんのところへ取材に行かなくちゃ。しかも崇高な目的を掲げて堂々とインドへ行けるチャンスなのではのではなかろうか?と思い立った。
連絡を取ってみると、「年明けに少人数のツアーがありますがご一緒しませんか?」との返答。なんとも絶妙なタイミングに興奮しつつメンバーを聞いてみると、また楽しそうな方ばかり。
私は二つ返事で、憧れのインドへ行くことになったのだ。
インドでは国内をあちこち回った。デリー → デラドン → デリー → コルコタ → デリー。全て布にまつわる旅である。

布の仕事のことを語る前に、憧れてやまなかったインドの片鱗を少々語ろう。
コルコタの街で受けた衝撃は、私が見てきたこの半世紀の全ての時代が一つの景色になっているということ。
いや、私が生まれる前の様子もしっかりと混じっている。ハイブリットカーと人力車やトゥクトゥクが並んで走り、ルンギやサリーなどの民族衣装を着た人々と、アディダスなどのスポーツウエアにスニーカーの若者や、日本と変わらぬ値段のハイファッションに身を包む人々が、屋台や路面店が密集した景色を背景にうごめいている。

やはりインドの人々には伝統的な衣装がぴったりとはまり美しいしカッコ良い。
個人的にはおじさま、おじいさまたちが渋くてカッコよくて素敵だと感じた。伝統服に身を包んだ人々は年配者が多く、街中の10%くらいはいただろうか。そんな人に会うたびに私は追いかけたくなり、彼らの生活に触れてみたい衝動にかられるも、ぐっとこらえてその時しなくちゃいけないこと、早々この場合は布の仕事場を見て回るということ、に集中集中。
はたき売りのおじさまのファッションセンスと色にしびれませんか?

街の小道を曲がると、鮮やかな色があちこちに。
私の住んでいる沖縄にもこんな色の組み合わせはほとんど出会わない。
インドの植物たちの色、インドの人々の褐色の肌が映える色、見ていて心にスパイス注入の元気色。
まるで街全体がインドのキルト、「カンタ」のように様々な色で彩られていて、歩いているだけでも楽しい。けれど、みんなスモッグがほんのりとついている。もちろん私の鼻の穴や、身体のあちこちにも。ハンカチでぬぐうとうわお、真っ黒。
日本の高度成長期にも見られた、砂塵と排気ガスと、スモッグと。近代化に向かう途中で人々が通る道。
そんな排気ガスやPM2.5が煙った街とは打って変わって、布の産地の村を訪れるとそこはなんとも豊かな世界が待っていた。

コルコタ市内から車で片道3時間ほどで着いた小さな村。
村の人々は純朴だ。私たち日本人の小さな集団を見つけると、はにかんで笑いながら挨拶をしてくれる。中にはスマホを片手に写真や動画を撮りながら後をついてくる人々も現れ、私たちの後には人だかりができた。
そして、私の予想に反して、村に工房らしきものは見当たらず、織り子が一人か二人が身を置く小屋のようなものが一つか二つあるばかり。

しかもほとんどの織り子さんは男性だという。織り子という言葉を使っていいのかどうか考えてしま位、ちょっとだけ面食らってしまった。
それでも手馴れた動きや、布を織る静かな時間が伝わってくると、私の思い込みもこれもありだとすんなりとその時間に溶け込んだ。
男性の織る布はきちっと滑らかに織り上げられてゆく。すとんすとんとリズムよく、心地の良い音が響く。
この村で織られているカディの糸は極細で、織り上がるとまるで風に色がついたような軽やかさを感じた。その縦糸と横糸にジャムダニと呼ばれる柄が織り込まれてゆく。
工房がない、織り子さんは男性。
服作りをするのにはどんなに小さくても20~30人くらいの織り子さんを抱える工房があるものだと思っていたし、そこで働く人々は日本のように女性だといつの間にかそんな思い込みが私の中にあったのだ。それまで抱いていた私の中の常識は、この旅で軽い驚きとともに崩れ去った。思い込みや常識が崩れる感覚が大好きな私は、また一つ世界が広がった気がして爽快感を感じていた。
女性の織る布はふくよかだ、これも思い込みかもしれない。この時、インドの男性の織る布は理数系的な感じがした。これは感覚なので今はまだうまく言葉で説明するのは難しいけれど、行き当たりばったり的な感じではなくて、柄の配列が数式のように整っているように感じられたのだ。
性別は関係ないのかもしれない。文化や歴史的背景やいろいろあるだろうが、それももしかしたら無関係で、この人の持つ世界観なのかもしれない。その追求は妄想なのでここではそっと置いておいて、何か言葉で表現するとするならば。
鼻歌というより、楽譜のある演奏という感じだろうか。いつかもっとうまく表現してみたい。

ここでインドの伝統的な織物カディのことを書きたい。
カディは布の原点と呼ばれている。
3000年前に書かれたインドのヴェーダという文献の中にも嫁入り道具としてカディの機を持たせるという一文が書かれているのだそう。また紀元前327年にアレキサンダー大王がインドに侵攻した際にこの生地に魅了されたというのは有名な話なのだそう。
近代になってインドの独立の父マハトマ・ガンジー氏がカディの生産を推奨し、国産品としての地位を固めたと言える。
彼は、「国産品のない独立は、生命のないただの屍にすぎない。国産品が独立の魂であるならば、カディこそが独立の根幹だ」といい、自らチャルカ(糸紡ぎ機を回して、その紡いだ糸で服を作り、それを独立運動の制服として着用した。1921年に「自分が纏う衣服のための糸を自らの手で紡ごう」という運動を起こし大きなうねりとなった。そうして独立運動は勢いを増し、カディの生産がインド中に広まっていった。
一人の織り子の周りには10の仕事ができると言われていて。当時何十万人いやもしかしたら何百万人ものインドの人々が職を得たという。
私は30年以上前からカディを手に取り、着ていたもののこのことをしっかりと知ったのはCALICOの小林史恵さんに出会ってからだ。知った時には深く深く胸を打たれた。
言葉や、その国の食文化、衣装には長い時間をかけて積み上げてきた民族の魂が宿っている。アイデンティティとも言えるだろう。それを失うと、国民はアイデンティティの喪失感から国土に根ざしていた根を断たれてしまう要素が多々ある。国産品を代々伝わってきた布文化の中に見出したことで、インドという国はいまだ強いアイデンティティを失わないまま近代化をも達成していることを感じる。様々な意味で豊かで、底の見えないたくましい国だと感じる。

織り子さんのいる小さな村である家族に呼び止められて彼らの住む家に招かれた。ものにあふれた私たちの生活から見ると、質素な暮らしに見える。半分以上も瓦のないトタン屋根、土間の暮らし。私の中にあった、インドは不衛生で薄汚れているのではないだろうか?そして相当人にぼられて精神的によっぽどタフでないと楽しい旅はできないだろう、というイメージはこの旅で吹き飛んでしまった。
街中にはきっとそんな側面もあるのだろうが、招かれた小さな村の家族のこの家は美しく掃き清められ、土間の緩やかな曲線はあちこちが美しく光っていた。そして彼らの柔らかく純粋な笑顔には豊かさが満ち溢れているのだ。
左は時のお母さんは陶工。地面に並んでいる器たちは素焼きでインドでは日常的に使われるものだ。整形して天日で乾かして、その後穴窯に入れられて焼かれる。家族の絆は強くたくましく明るくて、健康的で本当に美しかった。そんな人々に触れ合うと、生命力が充電される。元気もりもりの私はこの旅で全くお腹を壊さなかった。余談だが。
こんな村の家族のつながりや、親戚たちや隣人が職業や生産品でも強く結びついていて、村はとても健全だ。それがインド全土に広がっていることを思うと、やはりインドは強い国だ。近所や親戚や、もしや家族間の結びつきさえ薄くなって行く私たち先進国の暮らしの方がずっと脆弱に感じる。豊かさは金銭では決して測ることはできないし、幸福度はきっと人々の絆が深かければ深いほど得られるのではないか、私にはそう感じられた。
手の仕事が生きている土地の豊かさに触れたインドの旅。
ああ、なんか終わりそうになってしまったが、最後に今回の豊かな旅のきっかけになったCALICO:the ART of INDIAN VILLAGE FABRICSの仕事のことをちゃんと伝えたい。

布を織るのは男性の仕事というインドで、珍しい女性の織り子さん。最近は少しずつ女性も仕事をする機会が出てきているという。窓から目を輝かせて眺める少女たちが大人になる頃には、きっと今よりずっと女性たちの社会的な立ち位置は変化していることだろう。
『インドの小さな村に暮らす人々の、手紡ぎ手織りで仕上げられたカディのもつ自然な揺らぎは美しい。そのカディで仕立てられた服の中でも。CALICO:the ART of INDIAN VILLAGE FABRICSのデザイナー小林史恵さんが提案する服には、一本の芯が通った美を感じる。彼女は洗練された形を追求し、着る人の美意識を満たすだけではなく、生産者から最終消費者に至るまで、関わる人全員が対等で健全な経済的バランスの中にいることを目指している。歴史・文化背景の違う両国を行き来して互いの経済的自立と、仕事の喜びがもたらす複合的な利益のバランスをとるということは決して簡単なことではないだろう。それは彼女自身が「自分が見たい社会」を作るという信念を持ち。CALICOの全活動に意義を見出しているからこそできることだ。インドの布に魅せられて始まったこの仕事、「カディは村という太陽系における太陽であり、その営みなしでは他の惑星は成り立たない。村の人の空いた時間を有効利用するためにもチャルカ(糸車)を回し続けなければいけない」というマハトマ・ガンジー氏の言葉が一番しっくりくるという。
美意識と信念と行動が伴った人の生きる姿勢には人々を巻き込むパワーがある。裾を風になびかせてインドの村をしなやかに歩く彼女の姿を見てCALICOの服を無性に着たくなった。
私はかっこよく、美しいものだけに巻かれたいのだ。 田原あゆみ』
この文章はCALICOのDMを作った時に何日も何日も身悶えしながらまとめた文だ。書いてしまうとシンプルでサラッと読めるから読んだ人に産みの苦労は伝わるまい。しかし、彼女の活動の広さと心意気を知ってしまうとあれもこれも伝えたくなってしまい、まとめるのは本当に大変だった。
そしてこの記事を読んだみなさんにどうしてもこの豊かさに触れて欲しい。一人より二人、二人より四人、できるだけ多くの仲間友人家族知人に伝えて、このインドの手仕事カディの魅力と、小林史恵さんの活動の素晴らしさに触れて欲しい。
2018.04.26